対談企画:筑波大学ラグビー部OB会 中川会長 / 日本ラグビーフットボール協会 岩渕専務理事
筑波大学ラグビー部のアイデンティティを紐解く対談企画
「大学ラグビーの意義と筑波大学ラグビー部の果たすべき役割」をテーマとした中川会長、岩渕専務理事の対談記事の一部を先読み!
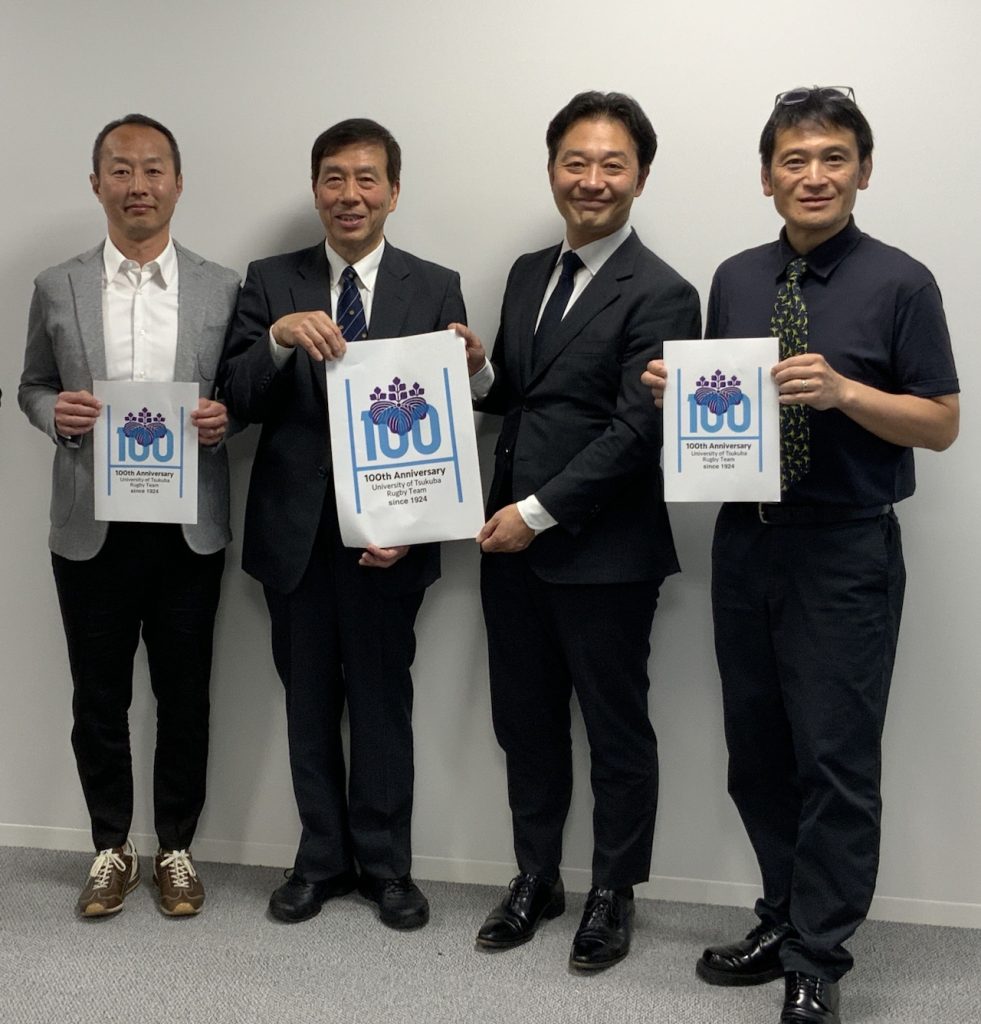
――中川昭先生が筑波大学ラグビー部の監督に就任された1994年度に、岩渕健輔さんが青山学院大学に入学されました。まずはお互いの当時の印象から聞かせてください。
中川 「ファンタジスタ」という言葉がありますが、まさにその通りの選手でしたね。筑波としては、まず岩渕さんをどうやって抑えるか、ということが青山学院と戦う時の最重要テーマで、4年間ずっとそうでした。それでもずいぶんやられましたが(笑)。
岩渕 高校時代に試合をした同級生のSO高橋修明やFB浦田昇平らが1年生の頃から出ていましたし、寮がないなど環境的に似ているところもあって、筑波には勝手に親近感を抱いていました。一方で「すごく練習しているらしい」という噂も聞こえてきていて、「ウチは週3回しかやってないよ」といった話をしていましたね(笑)。結局、筑波には4年間で一度も勝てませんでした。
中川 対抗戦の一番最後にやることが多かったですよね。そういうこともあってか、青山学院と筑波はOB同士が仲がいいんです。試合が終わってからOBだけでお酒を飲みに行ったりして、私もそうした会に参加したことがあります。
――関東大学対抗戦における立ち位置も、当時は似ていましたね。
岩渕 その頃は明治、早稲田、日体大が強くて、どうやってその3つの間に割って入っていくかという状況でした。その中で大学選手権に出るためには、筑波に勝たなければならない。「向こうも寮はないし、活動環境は変わらないんだから」といいながらやっていました。
中川 当時は早稲田、明治、日体が大きな壁で、慶應には青山学院もウチも時々勝ったりしていました。その4校をなんとか乗り越えようという位置に、帝京を含めた我々がいて、だから親近感があったのだと思います。以前は大学選手権の前に関東大学リーグ戦との交流試合(※編集注/対抗戦とリーグ戦の1〜4位がたすき掛けで対戦し、勝者が大学選手権に出場する)があって、その後、選手権の出場枠が5校になったのですが、上位4校のどこかに勝った上で、さらに青山学院、帝京、ウチの中で勝ち抜かないと選手権には進めないという状況だったんです。しかも筑波と青山学院は対抗戦の一番最後に対戦することが多くて、その試合に勝ったほうが選手権に行けるというケースもありました。
岩渕 私が入学する前の年に対抗戦の出場枠が5校になって(※編集注/1993年度に大学選手権出場校が16校に拡大され、交流試合が廃止に。対抗戦の5位は関東第5代表決定戦に勝利すれば選手権に出られるようになった)、1年生の時は対抗戦5位で大学選手権に出られたんです。でも2年生以降はずっと6位で出られませんでした。
中川 岩渕さんが入学した年は、筑波は青山学院には勝ったんですけど慶應に負けて、大学選手権に行けなかったんですよ。当時の対抗戦は慶應と帝京が対戦しなかったりして、順位決めにも変なルールがあった。絶対ウチのほうが上のはずなのに、なんでこんなことになるんだ、とがっかりしたことを覚えています。
――ラグビーのスタイルについてどんな印象を持っていましたか。
岩渕 きっちりしている、というイメージでした。全員でひとつの方向に向かって、やろうとしていることを15人全員でしっかり、正確にやるというチームですね。青山学院は、私自身もそうですが、みんな適当だったので(笑)。ハマった時は勢いに乗っていけるけど、そうじゃない時の波が激しかった。全員が正確に、お手本のようなプレーをする筑波とは、まったく違うスタイルでした。
中川 青山学院はすごく自由奔放で、セオリーではなかなか止められない部分がありました。勢いがつくと手がつけられなくなるチームで、その代表格が岩渕さんだった。流れを渡したら理屈じゃない力を発揮するので、それを出させないようにするのが、戦う時の最重要テーマでした。
岩渕 青山学院としては筑波はやりにくい相手でしたね。きっちり戦ってくるので、リズムを出しにくい。そしてリズムを出そうとしたプレーを止められると、どんどん筑波のペースになっていく。打ち合いにさせてもらえないチームでした。比較すると、慶應のほうが特徴がはっきりしていたのでやりやすかった。筑波はBKにもたくさんいい選手がいましたし、トータルで一人ひとりのプレーが正確という感じでした。ボールも取れないし、いったんボールを渡すとなかなか返ってこない。点を取られるまでそれが続いてしまうという印象です。
中川 青山学院は岩渕さんのようにマークしなければならない選手がはっきりしていたので、この選手とこの選手をビシッと抑えれば、というチームでした。我々としては、対策を立てやすかった印象があります。
――当時からそうやって細かく対策を立てていたのですね。
中川 そこはずっとやっていました。筑波はいわば弱者の論理で、力で及ばない相手にどうやって勝つチャンスを見出すか、ということを常に考えて準備するんです。そのためには相手の弱いところを突く、あるいは相手の強みを出させないようにすることが一番大事になる。そうやっていかないと勝てなかったですし、ここは筑波の文化としてずっと受け継がれていると思いますね。
岩渕 当時を振り返ると、我々は相手のことを考えるレベルにはありませんでした。もちろん監督やコーチはいろんなことを考えてくれていたと思いますが、相手がこうくるからこうするというよりも、自分たちがどうプレーするかということに主眼を置いていました。自分たちの色をどう出すかということを、常に考えていたように思います。中川先生ももちろんそうですし、最近はオリンピック委員会で筑波大学のいろいろな先生と接する機会がよくあるのですが、スポーツを科学として考える、という視点をすごく感じます。私は少なくとも大学時代にそういう発想はありませんでしたし、青山学院としてもなかったと思います。勝てなくて当然ですね(笑)。
中川 筑波大学には体育専門の学部があって、その中に「ラグビーコーチング学研究室」というものがあるんです。そこに教員がいて、それも一人じゃなく当時から3人くらいいました。そういう研究室がそれぞれの競技にあって、学生も3年生になると希望者がその研究室に所属する。そこでやるのが、スポーツをどうやって科学的にとらえるかということで、その一番わかりやすいものが相手の分析です。その方法を研究して実践することが、大学の教育の中に組み込まれていたことも、非常に大きな要素だと思いますね。そういうことをやるのが当たり前の環境があって学生も勉学として取り組めるわけですから。サッカーで筑波OBの三苫薫選手が、ドリブルを研究して卒論にしたということが話題になりましたが、そういうことを学生がやるという点は、筑波のラグビーを色づける特徴だと思います。これは東京教育大の頃から続く文化で、私が監督として筑波に帰ってきた時も、すでに学生が自らそういうことをできるチームでした。試合に出られない選手がラインアウトの分析をしたり、相手がやってくることをわかった上で試合をしていました。
岩渕 だから、みんなが同じ方向に向かってきっちり戦えるんですね。
中川 その研究室には大学院生もいて、修士や博士も取れますから。ちなみに今の嶋﨑達也監督は、私がいた時の研究室の学生です。
岩渕 前監督の古川拓生さんは、私が日本代表だった時のコーチでした。その頃から、筑波出身のスタッフの方は多かったですね。勝田隆さん、宮尾正彦さん…。最近では中島正太さんが、アナリストとして日本代表をサポートしています。
中川 最近は、最初からそういう道に進みたいといって筑波に入ってくる学生もいるんですよ。
岩渕 大学の時は、そんな研究をしているなんて知りませんでした。知っていたら、もう少しうまく戦えたと思いますが(笑)。
――1994年に筑波の監督に就任した時、中川先生はどのようにチームを強化しようと考えていたのでしょうか。
中川 私は東京教育大の最後の代で、大学を卒業して筑波大学の大学院に入った時に学生コーチをやったのですが、その時に来たのがジム・グリーンウッドコーチなんです。ジムはスコットランド代表のキャプテンも務めた名選手でもあり、イギリスのラフバラ大学の監督をやっていた非常に有名なコーチでもありました。
ジムのラグビーはすごく先鋭的で、ボールをいかにスペースへ運ぶかという点で、それまでの日本にはなかった斬新な発想をたくさん教わりました。パスひとつとっても、今は誰もが普通にスクリュー(スピン)パスをしますが、当時はストレートパスばかりで、ジムが初めてスクリューパスを教えてくれたんです。SOからCTBを2人飛ばしてFBを入れるなど、スクリューパスを使ってスペースを攻めるアタックをやったのも、日本では筑波が初めてでした。ジムはよく、「相手に何をやってくるかわからないと思わせないと勝てない」ということをいっていました。
それが1979〜80年ですが、その後私は大阪の大学に勤めたので、10年ちょっと筑波のラグビーから離れていたんです。それで1994年に戻ってきた時、その財産がほとんどなくなってしまった――という印象を受けました。だからもう一度ジム・グリーンウッドの考え方を注入できないかというのが、監督に就任して最初に考えたことです。
続きは、記念誌にてお楽しみ下さい。。

